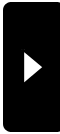2006年11月27日
乾電池の寿命(保存の寿命)
皆さんの家庭でも何本かの乾電池の買い置きはあると思います。災害時に必要なものとして懐中電灯やポータブルラジオには乾電池が必要となりますので、必ず予備の乾電池も備蓄するのは当たり前となっています。
さて、先日私の使っている3セルDのマグライト(単1電池を3本使うタイプ)の乾電池をそろそろ交換しようと思い、乾電池を取り出してみたら電池の底が少し湿って液漏れが始まっていました。私のマグライトは標準のクリプトン球からクセノン球へ変更して更にLEDへ変更した為電池の持ちが良くなった為2年ほど乾電池を入れ替えてませんでした。早速買い置きの電池へ交換しようと思い、新品の単一の電池を出してみたら未使用にも関わらず、液漏れを起こしていました。電池に表示されている使用推奨期限を見てみると2004年になっていました。こりゃイカンということですべての買い置き電池を調べてみると期限切れが多くもったいないですが廃棄することにしました。電池の買い置きは必須ですが乾電池にも保存する寿命があることを思い知らされた一件でした。
ちなみに、単一・単二は3年、単三・単四・単五は2年、の使用推奨期限が設けてあるそうです。
2006年11月14日
アルコールストーブの魅力
アルコールストーブとして超定番の「トランギア・アルコールバーナー」ですが、恥ずかしながら今年になるまで使ったことがなかった。シングルバーナーではプリムスの初期型2243とイワタニのジュニアバーナーを所持しているので、パッキングは多少悪いですが、不便はしていなかった。
実は去年、災害ボランティア仲間の知り合いから、十字に組み合わせて使うチタン製の五徳をもらっていた。何に使う五徳かはおおよそ検討がついていたが、すぐに使う必要も無かったのでしばらく放って置いていたのだが、今年になって勤めていた会社を辞め、もともと自営業をしていた自宅に事務所を構えるようになって、デスクの近くでコーヒーを沸かす道具が欲しくなった。ジュニアバーナーは普段、寝室で夜食のカップラーメン用に使っているので使いたくない。2243は普段使うにはガスが高いので使いたくなかった。そこで、アルコールバーナーの購入となったわけである。さっそく通販で購入し、火力についてあまり期待をしていなかったが、トランギア製の0.9Lのケトルでコーヒー一杯分のお湯を沸かしてみた。すると期待していた以上に強い炎で数分で沸かすことができた。 しばらくはチタンの五徳(商品名は「アリゾナストーブ」現在は売られていない)を使っていたのだが、ケトルの直径よりも小さい五徳に不安を感じたので、何か変わりになるものを探していたら、以前キャプテンスタッグ製の固形燃料を使ったコンロを買ったことを思い出した。組み立て式で黒い円筒状の部品を組合せ五徳をはめる構造になっている。これも早速使ってみた。ケトルの安定もいいし五徳を持ち上げる取っ手も付いているので非常に都合が良かった。ただ、炎からの五徳までの高さが高すぎるので2段に組み合わせていた部品を、1段(円形の空気穴があるほうだけ)にしたら更に良くなった。
しばらくはチタンの五徳(商品名は「アリゾナストーブ」現在は売られていない)を使っていたのだが、ケトルの直径よりも小さい五徳に不安を感じたので、何か変わりになるものを探していたら、以前キャプテンスタッグ製の固形燃料を使ったコンロを買ったことを思い出した。組み立て式で黒い円筒状の部品を組合せ五徳をはめる構造になっている。これも早速使ってみた。ケトルの安定もいいし五徳を持ち上げる取っ手も付いているので非常に都合が良かった。ただ、炎からの五徳までの高さが高すぎるので2段に組み合わせていた部品を、1段(円形の空気穴があるほうだけ)にしたら更に良くなった。 では本来のフィールドでの使用についてはどうか。アリゾナストーブだけではやはり風に対して弱く、沸騰までの時間がかかってしまう。そこでユニフレーム製のシングルストーブ用の風防を手に入れた。この組合せが私の考えるベストかなと思っている。(ストームクッカーは本来のコンパクトさを欠いているのであまり好きではない)
では本来のフィールドでの使用についてはどうか。アリゾナストーブだけではやはり風に対して弱く、沸騰までの時間がかかってしまう。そこでユニフレーム製のシングルストーブ用の風防を手に入れた。この組合せが私の考えるベストかなと思っている。(ストームクッカーは本来のコンパクトさを欠いているのであまり好きではない)
 しばらくはチタンの五徳(商品名は「アリゾナストーブ」現在は売られていない)を使っていたのだが、ケトルの直径よりも小さい五徳に不安を感じたので、何か変わりになるものを探していたら、以前キャプテンスタッグ製の固形燃料を使ったコンロを買ったことを思い出した。組み立て式で黒い円筒状の部品を組合せ五徳をはめる構造になっている。これも早速使ってみた。ケトルの安定もいいし五徳を持ち上げる取っ手も付いているので非常に都合が良かった。ただ、炎からの五徳までの高さが高すぎるので2段に組み合わせていた部品を、1段(円形の空気穴があるほうだけ)にしたら更に良くなった。
しばらくはチタンの五徳(商品名は「アリゾナストーブ」現在は売られていない)を使っていたのだが、ケトルの直径よりも小さい五徳に不安を感じたので、何か変わりになるものを探していたら、以前キャプテンスタッグ製の固形燃料を使ったコンロを買ったことを思い出した。組み立て式で黒い円筒状の部品を組合せ五徳をはめる構造になっている。これも早速使ってみた。ケトルの安定もいいし五徳を持ち上げる取っ手も付いているので非常に都合が良かった。ただ、炎からの五徳までの高さが高すぎるので2段に組み合わせていた部品を、1段(円形の空気穴があるほうだけ)にしたら更に良くなった。 では本来のフィールドでの使用についてはどうか。アリゾナストーブだけではやはり風に対して弱く、沸騰までの時間がかかってしまう。そこでユニフレーム製のシングルストーブ用の風防を手に入れた。この組合せが私の考えるベストかなと思っている。(ストームクッカーは本来のコンパクトさを欠いているのであまり好きではない)
では本来のフィールドでの使用についてはどうか。アリゾナストーブだけではやはり風に対して弱く、沸騰までの時間がかかってしまう。そこでユニフレーム製のシングルストーブ用の風防を手に入れた。この組合せが私の考えるベストかなと思っている。(ストームクッカーは本来のコンパクトさを欠いているのであまり好きではない)
2006年10月24日
アメリカ製の七輪の実力

ノーブランド キャンピングストーブ セコイア
涼しくなり焚き火が恋しい季節になりました。私の悪い癖で何か新しい焚き火道具がほしくなり、ネットで見かけたこのアメリカ製の七輪(ネイチャーストーブというジャンルみたいだが)を購入してみた。さっそく使ってみようと、子供たちにせがまれていた鮭の燻製を作ることにした(うちの子供は燻製が大好きである)。スーパーから買ってきた甘塩のサーモントラウト(鮭ではなくニジマスの改良種)の切身を軽く塩抜きしてから、ペーパータオルで拭いて冷蔵庫で30分ほど乾燥させておく。本題の「セコイア」に火を入れるのだが、火力の強いオガ備長炭を使いたいのでまず着火剤に火を付け放り込み、次に火の付きやすいBBQ用の黒炭を入れた。普段はこの作業を七輪で行うのでその場合は、着火を助ける煙突状の器具を使うが「セコイア」では必要なさそうである。ただし、黒炭へ火が回る時間は七輪のほうが速かった。なぜならば、七輪に比べて直径が大きい為、炭が多いのと、「セコイア」は本体が温まらないと上昇気流が発生しないので(暖炉・薪ストーブと同じ原理)温まるまで時間がかかった。その後、オガ備長炭を入れて着火を待ったが、これは比較的速く着火できた。「セコイア」に中華鍋をのせ、スモークチップを入れてからサーモントラウトの切身をのせた丸網を鍋にセットした。チップから煙が立ち上がるのをみてからふたをする。出来上がりまで約1時間ほどかかるが、煙が上がり過ぎないように火力の調整をする必要がある。ここで少し問題が発生した。「セコイア」には空気の流入を制御する(ってほどでもないけど)レバーが付いている。説明書にもこれを開け閉めすることで火力を調整できる旨が書かれているが、途中にレバーを保てない。しかたなくレバーを近くにあったレンガでホールドして何とか調整した。燻製は完成し、火の始末にかかった。燃え残りのオガ備長炭は蓋のできる空き缶等にいれれば消し炭として再利用できるので、まず焚き火用トングで取り出した。綺麗に燃えたので後は細かい白い灰が残るだけ。で、再度問題発生。灰が出せないのである。七輪のように掃きだし口がないので灰が出せず、傾けてしまうと「セコイア」の内部の筒に入ってしまう。説明書きにも灰の取り出し方は書いていない。今回は灰の量が少ないので次回まで問題なさそうだが、もしいい方法を知っている方は是非教えてほしい。アメリカ人はこんなこと気にしないのかもしれないけど。 とりあえず使ってみて文句が出るようなものではありませんでした。庭先でちょっと焚き火をしてみたい方、落ち葉や枯れ木を使って煮炊きをしたい方、お薦めです。
2006年05月15日
ダッチオーブンのルーツ

LODGE(ロッジ) LOGIC ハーフピントサービングケトル
ダッチオーブンのルーツについては、いろいろな本に諸説が書かれている。有名なのはオランダ人がアメリカ西部で売り歩いた鉄鍋であるという事からダッチオーブンと名のついた説である。ではその形についてはどうなのであろうか。ある時ふと中国の故事を思い出した。「鼎の軽重を問う」と言う言葉(意味については自分でお調べ下さい)。この「鼎」であるが、ここを参照。3本の足のついた中国古代の鍋である。実際には煮炊きされたかは不明であるが、基本的には3本脚の下で火を焚いて使うものである。 LODGELOGICのハーフパイントサービングケトルを見かけたときはまさにその「鼎」の形そのままでした。現代における「鼎」、「ダッチオーブンの軽重を問う」とでも言いましょうか。
2005年09月27日
どこでも座れるお手軽な座椅子
平らなところがあれば直接座りたいのが日本人の感覚である。板の間であればキャプテンチェアでなくやはり座椅子が欲しくなる。アウトドア用の座椅子と言うと「クレージークリーク」が元祖だと思うがやはり元祖だけあって少しお高い。国産でも何社か同じような意匠で作られている。ロールタイプであれば持ち運びも便利で防災用品に付け加えたい。ちなみに一番値段が安いであろうC社の物を買ったが残念ながら体重を支えるフレーム(プラのパイプ?)が弱く、しなってしまうし、フレームの先端が当る生地部分が補強が無いのですぐに穴が開いてパイプが飛び出してしまった。購入の際はそこに注意をされたい。



 アウトドア&フィッシング ナチュラムが提供する、自然と戯れ、自然を愛する人々のBlogサイト
アウトドア&フィッシング ナチュラムが提供する、自然と戯れ、自然を愛する人々のBlogサイト